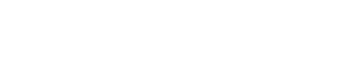株式会社トンボ楽器製作所
★このページは『TOMBO祭2024』のコンテンツであり、2024年11月24日時点の情報となります。
特別対談 未来へ繋ごう! ハーモニカの輪!
付録:登場人物紹介
大矢博文(おおやひろふみ)
日本を代表するコードハーモニカ奏者であり、独奏・合奏のハーモニカ指導者としても長年活躍していたものの、88歳となった現在は、ハーモニカ界から全て引退し、ノンビリと余生⁈を満喫中。
津田佳世子(つだかよこ)
小学校5年生からクロマチックハーモニカを伯父である大矢博文氏に師事。
ソリストとしても精力的にコンサート活動を展開し、指導者として後進の指導にも活躍。
CDアルバム「あなたに感謝」が好評発売中!

オジョイメイ・トリオ(2002年当時)
左から大矢博文、津田佳世子、吉田俊輔
ジェリー・ムラッド、ハーモニーキャッツ(Jerry Murad's Harmonicats)
1947(昭和22)年に結成したされたアメリカのハーモニカトリオ。クロマチック、コード、バスの3本のハーモニカにより様々な曲を奏でて一世を風靡し、ハーモニカアンサンブルの代名詞のような伝説的な存在。
ジュディーズ・ハーモニカ・アンサンブル (Judy's Harmonica Ensemble)
世界トップクラスの人気と実力を兼ね備えた、台湾のハーモニカアンサンブルグループ。
2013(平成25)年のワールド・ハーモニカ・フェスティバルでトリオ世界チャンピオンのタイトルを獲得し、国際的に知られるようになる。クラシックやポピュラーミュージック、オリジナル曲などレパートリーも幅広い。
リーダーはクロマチックハーモニカ奏者のチャン・チューティン(Chu-Ti Chuang)。
YouTubeでも演奏動画を公開中。
フレスコ・ハーモニカ・アンサンブル (Fresco Harmonica Ensemble)
抜群のテクニックに加えて、ステージを〝魅せる〟ことに工夫を凝らして観衆を魅了するマレーシアのハーモニカアンサンブル。2009(平成21)年、2013(平成25)年と国際コンテストで連続優勝。
アドラートリオ (The Adler Trio)
1995(平成7)年の横浜世界大会の際に初来日し、圧倒的なテクニックとスピード感溢れる演奏で聴衆を釘付けにした〝世界最高峰〟のイスラエルのハーモニカトリオ。現在は活動を終了しているが、今も世界中に熱烈なファンが多い。
斎藤寿孝(さいとうじゅこう)
高校時代に複音ハーモニカを佐藤秀廊氏に師事し、全日本学生ハーモニカコンクール等で優勝。ハーモニカ団体の要職を長年務める他、プレイヤーとして、指導者として活躍し、〝ペンタトニックハーモニカ〟を開発する等、各方面で活躍。
宮田東峰(みやたとうほう)
1918(大正7)年中央大学在学中に日本初のハーモニカ合奏団(後のミヤタ・ハーモニカバンド)を結成。1925(大正14)年には自身監修の「ミヤタハーモニカ」を発売し、パッケージに自身の顔写真を採用したこの複音ハーモニカは爆発的な人気となった。1986(昭和61)年1月、87歳で没。
佐藤秀廊(さとうひでろう)
20代前半の頃、当時玩具視されていたハーモニカに、分散和音奏法、ヴァイオリン奏法、マンドリン奏法などの日本的奏法を創案し、これを高度に生かした編曲によって芸術性を高め、1926(大正15)年ドイツで開かれた〝ハーモニカ100年祭〟に日本代表として参加し、コンテストで優勝。1990(平成2)年10月、90歳で没。
岩崎重昭(いわさきしげあき)
10歳の頃に初めて複音ハーモニカを手にし、その後に日本を代表する奏者である佐藤秀廊氏や川口章吾氏に師事。長年、地元厚木市を中心に多くのハーモニカ教室を主宰し、〝ハーモニカのまちあつぎ〟の礎を築き、2002(平成14)年に厚木市で開催されたアジア太平洋ハーモニカ大会では審査委員長を務めた。2015(平成27)年7月、87歳で没。
ラリー・アドラー(Larry Adler)
10歳の頃からクロマチックハーモニカを独学し、1927(昭和2)年、13歳の時にコンテストで優勝、以降ハーモニカ奏者として活動するようになった。ハーモニカという楽器のイメージを全く覆してしまった天才であり、〝キング・オブ・ハーモニカ〟と呼ばれる。2001(平成13)年8月、87歳で没。
ピート・ピーダスン (Pete Pedersen)
若い頃、ボラ・ミネヴィッチ率いる「ハーモニカラスカルズ」のメンバーとしてハーモニカを吹きながらステージを転んだり滑ったりするボードビリアンとして活躍。プレイヤーとしてだけでなく、作曲家、編曲家、プロデューサーとしても活躍し、〝ハーモニカの魔術師〟と呼ばれる。2002(平成14)年5月、76歳で没。
クロード・ガーデン (Claude Garden)
フランスのクロマチックハーモニカ奏者で、クラシックからジャズまで幅広いレパートリーを持ち、その音色をハーモニカはもちろん、時にはオーボエやヴァイオリン、オルガン等を思わせるように多彩に変化させて聴衆を魅了した。2004(平成16)年12月、67歳で没。
シー・ワイ・レオ (Cy Leo)
香港出身のハーモニカプレイヤーであり、作曲家、シンガーソングライターとしてジャンルを超えて世界で活躍中。
2009(平成21)年と2013(平成25)年のワールド・ハーモニカ・フェスティバルで世界チャンピオンに輝くなど、17の国際タイトルを獲得。
ハーモニカの枠にとらわれない幅広い音楽活動を行っている。
森本恵夫(もりもとよしお)
戦後から日本のハーモニカ界の第一人者として、複音ハーモニカ及びクロマチックハーモニカの両方で活躍。国際コンテストでの上位入賞歴も多数あり、映画音楽、テレビ音楽、レコード音楽、コマーシャル音楽等の分野で新境地を開拓し、生涯のレコーディング曲は20,000曲を超える。2020(令和2)年2月、97歳で没。
ザ・ブルー・ハーモニキャッツ (森本恵夫とザ・ブルー・ハーモニキャッツ)
森本恵夫(クロマチック)、波木圭二(コード)、鶴田亘弘(バス)の3人による世界に誇る日本の伝説的なハーモニカトリオ。1971(昭和46)年ドイツで開催された国際ハーモニカテープコンテストで 第2位受賞。
京都ハーモニカクヮルテット
ハーモニカ奏者、指導者として関西を中心に長年活躍された巨匠、故井上隆寿氏(初代リーダー)、故小林忠夫氏(2代目リーダー)らを中心に戦前から結成され、メンバーを入れ替えながらもグループ名を引き継いで活動する日本屈指のハーモニカアンサンブル。4代目にあたる現メンバーは、1993(平成5)年、1995(平成7)年と国際コンテストで連続優勝。
徳永延生(とくながのぶお)
1950(昭和25)年生まれ。1995(平成7)年横浜で開催された世界大会では日本代表としてJazzのガラコンサートに出演。ハーモニカ教室を多数開催し、後進の指導にも力を入れ、その生徒の中からは国内外のコンテストでの優勝者や上位入賞者を多数輩出。独自の音色や奏法を研究・考案し超絶なテクニックを駆使した個性的でダイナミックかつ繊細なサウンドは〝Tokunaga Sound〟として高く評価されている。
南里沙(みなみりさ)
1987(昭和62)年兵庫県出身。3歳でピアノ、12歳でオーボエを始め、神戸女学院大学音楽科オーボエ専攻卒業。大学在学中にクロマチックハーモニカに出会い、音色に魅せられて徳永延生氏に師事。国内外のコンテストで多くの優勝を果たし、2013(平成25)年キングレコードよりメジャーデビュー。
山下伶(やましたれい)
1987(昭和62)年埼玉県出身。桐朋学園芸術短期大学ではフルート専攻だったが、卒業後の2011(平成23)年にクロマチックハーモニカの存在を知り、徳永延生氏に師事。2014(平成26)年全日本ハーモニカコンテストでは3部門で優勝し、同大会の全部門の中で総合グランプリも受賞。2016(平成28)年ビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー。
ハーモニカラスカルズ
(ボラ・ミネヴィッチとハーモニカラスカルズ Borrah Minevitch & His Harmonica Rascals)
ボラ・ミネヴィッチ率いるアメリカのハーモニカを中心としたコミック・バンド。1933(昭和8)年にレコードを発売し、映画出演やショーでの演奏で大活躍。リチャード・ヘイマン、ジョニー・プレオ、ジェリー・ムラッド、ピート・ピーダスン等、著名なハーモニカ奏者を多く輩出した。コミック・バンドとしてのパフォーマンスの面白さはもちろん、その演奏技術の高さにも驚かされる。
リトル・フラワーズ
地元厚木市を中心に数多くのハーモニカ教室を主宰していた名指導者、故岩崎重昭氏の自宅教室に通う同い年の4人で結成され、小学5年生、6年生の時には全日本ハーモニカコンテストのアンサンブル部門で大人も含めた中で2年連続優勝を果たす。グループ名の由来は、岩崎氏の本業が種苗店だったことから〝小さなお花達〟となった。