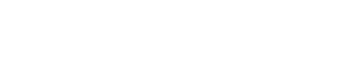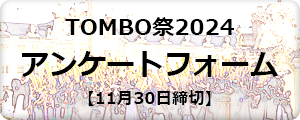株式会社トンボ楽器製作所


★このページは『TOMBO祭2024』のコンテンツであり、2024年11月24日時点の情報となります。
アコーディオン活用の多様性
KEIKO(音曲パフォーマンス)
はらよし:
TFC-On-Lineの担当ならびにTOMBO祭の実行委員長の“はらよし”と申します。
この度は『トンボ楽器製作所』エリア、ピックアッププレイヤーのインタビューにご協力いただきありがとうございます。
アコーディオンという楽器は実に多彩な表現が可能である、と感じさせてくれる場面の一つに『演芸』があります。
戦後復興の中で育ち愛された大衆音楽と、ハーモニカやアコーディオンの音色には強い結びつきを感じます。
そんな昭和の大衆文化は令和の時代に入り、一周回って若い世代の興味も惹いている、なんてニュースも耳にします。
KEIKOさんは『音曲パフォーマンス』という肩書きでアコーディオンを用い、寄席を始め色々な場所で芸事を披露されています。
まずは簡単なプロフィールをお聞かせください。
KEIKO:
KEIKOです。大分県佐伯市で生まれ、熊本県で育ちました。18歳の大学入学とともに東京に出てきました。
22歳、看護大学の実習が終わり、「卒業までにやりたいことをかじりたい」と思ってアコーディオンを始めました。元々お笑いが好きだったので、アコーディオンを習うにあたっては「音曲芸人」の門をたたきました。
はじめたが最後、終わり方がわからず今まで続いています。寄席からイベント会場まで、さまざまなところに伺います。英国発のおもちゃ屋さん「ハムリーズ」で定期的に演奏していた時期もあります。現在は、東京演芸協会に所属してます。

英国発!世界最”幸”の玩具店「ハムリーズ」にて
はらよし:
ありがとうございます。
「看護」と「お笑い」、接点がなさそうな世界ですが、ケアという意味では実は繋がりが深いのかもしれませんね。
「ハムリーズ」という玩具屋さんをはじめて知りましたが、世界最古のおもちゃ屋さんなんですね。
トンボ楽器の前身も『高陽堂真野商会』という玩具問屋で、1911年(明治44年)にオリジナル玩具として金属リードを使った音の出る風琴玩具を販売しています。
こういった玩具が持つ遊び心は、お笑いとも通じるところがあるのかもしれませんね。

KEIKOさんがいわゆる演奏家としてのアコーディオニストではなく、パフォーマーを選択した理由は何でしょうか?
また、相方にアコーディオンを選択した理由もお聞かせください。
KEIKO:
まず、私が習った先生が、演奏家ではなく芸人だったというところが一番大きいかと思います。
いろんなことができるようにと、バルーンアートやマジックの技術も授けてくれました。
私も素直に楽しんでやっていました。
そもそも、アコーディオンをやるにしても、漫才協会のおしどりさんや、昭和の名人芸に出てくるような横山ホットブラザーズさんや東京ボーイズのお師匠さん方が好きではじめています。
東京に出てきてから、大道芸で弾く姿もみて「あんな感じもいいなぁ」と思った記憶もあります。
ですので、いわゆる「演奏家」になることは最初から頭にはなかったようで、反転してパフォーマーになりました。
アコーディオンは電気も使わずに和音が出てくれます。しかも持ち運び自由。この2点がはじめた最大の理由かと思います。
現場に行って、人に借りて演奏するとか苦手なんです(笑)

風速8mの中「亀戸大道芸ホコ天レトロフューチャー」。
後ろにも色とりどりの芸人さんがいます。
新型コロナウイルスで規制がかかる直前の大きな大道芸フェスティバルでした。
はらよし:
なるほど、アコーディオンとの出会いは芸人さんだったのですね。
おっしゃる通りアナログ楽器の利点の一つは電源不要なので、場所を選ばず演奏できるところにあります。
アコーディオンにはベースボタンがあり、伴奏ができますので、ソロでも複数でもマルチに活躍することができます。
KEIKOさんはバロンブリーニ社製のアコーディオンを使用されていますが、購入の決め手となったのはどんなところでしょうか?
KEIKO:
私の先生も、その先生(いわゆる大師匠)もずっとTOMBOさんユーザーです。
なので、アコーディオンの相談はTOMBOさんにしか行ったことがないです。気が小さいので他の楽器店に入ってもそそくさと出てきてしまいます。
このバロンブリーニは実は、私の先生から譲っていただいたものです。私は体が小さいのですが、コード数が多いものを選ぼうとするとどうしても大型に偏ってきてしまうため、見た目がアンバランスになります。
そんな時に、96ベースで34鍵盤で中型サイズの発売はベストオブベストでした。
はらよし:
アコーディオンを展示し、試奏が可能な楽器店さんは限られていますからね。
なお、トンボ楽器は自社でもアコーディオンを製造するメーカーですが、外国製アコーディオンの正規代理店としても輸入販売しています。
なお、現在バロンブリーニという会社は廃業し、二つのブランド名として残っています。
トンボではその一つ、ファビオ・バロンブリーニ(FBB)を取り扱っています。
というか、KEIKOさん、気が小さいのですか?(笑)
私たちが思い描く芸能人のイメージって、メディアを通した断片的なものから勝手に解釈していますが、実は○○だった、というのはトーク番組でも定番のすべらない話ですね。
KEIKOさんがお持ちのアコーディオンは34鍵ですが、この鍵盤数だと72ベースが多い中96ベースと充実しています。
小型、もしくは72ベースではベースボタンが少ない、と感じるのでしょうか?
また。コード数が多く欲しいというのは、色々な曲をそれに合ったキーで弾くため、という理由からでしょうか。
極端な話、転調すれば小型でも弾ける曲は多いと思います。
KEIKO:
自分だけで弾く時は転調して弾きやすいように対応しますが、歌声喫茶のようなお客さまに歌っていただく時に、多くのコードがあるととても助かります。
コロナの前は、懐かしの歌をたくさん歌おう!のような現場も多かったんです。歌本みたいなのを持ち込んで、1時間くらいずっと弾きっぱなし歌われっぱなしです。
その場でキーを変えることもよくあります。このコンテンツで、私の先生と一緒に豪華客船クルーズのお仕事にいったこともありました。
そんな時には小型アコーディオンだとどうしてもベースが足りなくなってしまいます。
はらよし:
やはり色々な曲やシチュエーションに合わせるために、最低限必要なベース数がある、ということですね。
KEIKOさんはコンスタントに寄席に出演されていますが、ステージをご覧になったお客様からはどのような感想をいただくことが多いですか?
ちなみに、私も拝見させていただきましたが、落語との対比という意味でも面白いと感じました。
落語で使用する小道具は扇子と手ぬぐいくらいで、これをあらゆるものに変え、実際に存在していると錯覚させてしまう話術があります。
演芸は実際に道具を使用してお客様を楽しませるわけですが、アコーディオンは単独の“音”として、また曲としての“音楽”を作る道具です。そこに歌とお話をミックスさせています。
音楽のリズムと話のリズムがピタッと合うと、お客様も同じ世界に入っていけるのだと感じました。
短い時間の中に、たくさんの想いが詰まった楽しいステージでした。
KEIKO:
お褒めいただきありがとうございます。慣れないので恥ずかしいです(笑)
感想は…「懐かしい」「珍しい」「左手の方どうなってるの、見せて」「重そう」等々…
そういえば、アコーディオンをはじめた頃に、傷痍軍人と言われたこともありましたが、時代でしょうか?なくなりました。
のど自慢の伴奏のイメージが世間的には強いようで、よくいわれます。

懐かしの昭和歌謡ユニットは人気です。
このようなイメージは根強いようです。
はらよし:
たくさんのボタンが整然と並んでいる様はビジュアル的にもインパクトがありますからね。
日本では傷痍軍人が弾く楽器として、アコーディオンのイメージがありますね。
傷痍軍人が登場する戦争ドラマが制作されるときには、弊社にもアコーディオンの貸出や出演の依頼がございます。
あと、やはりのど自慢のイメージもありますね。日本社会の成長過程でアコーディオンが果たした役割が、楽器そのもののイメージにも結びついているんでしょう。
そんな昭和のイメージが強いアコーディオンですが、時代は令和です。
新しいアコーディオンのイメージも、そろそろ作っていきたいですね。
KEIKO:
私が演奏する場所には大人の方が多いからかもしれません。
一時期は「SEKAI NO OWARI」!って言われましたし、「逃げるは恥だが役に立つ」の放送時には「チャラン・ポ・ランタン」!と言われました。メディアの力はすごいなぁと思います。
のど自慢のようにメディアで細く長くアコーディオンが使われることは現代では少ないかもしれませんが、若い世代でもアコーディオンが流行し、長く続いて欲しいですね!
はらよし:
そうですね。そのためにはメディアへの露出も重要になりそうです。
一旦演芸から離れます。
KEIKOさんの音楽ルーツはどこにあるのでしょうか。小さい頃に好きだった曲やアコーディオンに出会う前に聴いていた曲など教えていただけますでしょうか。
KEIKO:
ピアノは習い事として、親がさせてくれていました。バイエルはあんまり進まず、「月刊ピアノ」ばっかり進んでいました。
ピアノの先生が同じマンションの住人だったので、音が丸聞こえでバレていたようです。
中学と高校で吹奏楽部のパーカッションを担当していましたが、中高ともにゆるい部活だったので趣味みたいなものでした。
この時期はいわゆる青春ロックバンドばっかり聴いていました。
MD全盛期です。19、BUMP OF CHICKEN、ロードオブメジャー、175R、GOING STEADYあたりです。そこから遡って、THE BLUE HEARTSと、JUN SKY WALKERS 。
ロックと漫才が交互に流れるMDでした。
はらよし:
子どもの頃から音楽や楽器のある環境で育ったんですね。
そして青春時代はロックとクラシック(吹奏楽)、そこに漫才を混ぜてしまうのが将来を予見させます。
漫才も落語も、「間」ってとても重要ですよね。音楽だとリズムでしょうか。そこにアドリブというライブ感が加わると躍動感が増すのでは、と私は感じています。
寄席のお客様の年齢層はその時々で幅があると思いますが、演目はどのように決めているのでしょうか。
また、当日の雰囲気で変更することもあるのでしょうか。
KEIKO:
寄席に到着したら、なるべく、客席を後ろからこっそり確認しに行くようにします。
若い方や家族連れの方がいらしたら、最近の流行の歌を入れることもあります。
なるべく年齢層を合わせにいくようにはしていますが、外すこともよくあります。
まだまだ経験不足です。

2024年度 高円寺演芸まつりにて
はらよし:
なるほど。やはり当日の場を観察して決めているのですね。
ちなみにKEIKOさんは持ち時間が20分として、音楽的に例えるとどんなイメージ(構成)になるのでしょうか?
それぞれテーマごとに小曲をいくつか演奏する、関連性のある演目を繋げて組曲のようにする、20分の大曲にする、等々……
KEIKO:
音楽的な構成!そういう視点では考えたことがなかったです(汗)
イントロ→Aメロ→サビ→大サビ(アンコール)って感じでしょうか。
持ち時間は関係なく、起承転結で考えています。
起→自己紹介•楽器の紹介、承→小ネタ、転→盛り上がるような歌、結→終わると思わせてアンコール、というイメージです。
ひとつの「曲」自体はだいたい1分前後、長くても2分半以内におさめています。ひとつの曲が3分を超えると、長いと感じています。
小さな曲とお喋りを繋いで、起承転結を作るようにしています。
はらよし:
起承転結、確かにエンタメの基本ですね。1曲3分は確かに長く感じてしまいます。
曲によってはもっと聴きたい、聴かせたいというのもあるでしょうが、そこはパフォーマーとして割り切る必要があるかもしれません。
今さらではありますが、KEIKOさんにとってアコーディオンの魅力とは何でしょうか。
また演芸におけるアコーディオンの可能性やご自身が目指す芸についてお聞かせください。
KEIKO:
頑張らなくても和音が出る、持ち運びができる、これは最大の魅力です。
それから、吹く楽器ではないので、自由に喋ることもできるし歌うこともできます。
ですので、メインステージを張ることもできるし、逆に人を立てるような伴奏にまわることもできます。
一人でなにごとも完結する、素敵な楽器だと思っています。
日本一の「ひざ」になる、というのが目標です。寄席では、最後のトリの前に出る人のことを「ひざがわり」と言います。
この位置で自分が演技できるのは憧れですし目標です。
寄席はいろんな演芸が集まる場ではありますが、やはり噺家さんがメインの場が多いです。
主役はトリの噺家さんであって自分ではないし、自分は今日の公演が成り立つパーツだと思っています。が、お話とは違った魅力が音ものにはあります。
いてもらって助かった、よかったと言われる芸人になりたいです。
はらよし:
落語は面白くても4時間連続で聞きっぱなしだと、よほどの落語好きでない限りは流石に疲れますし、集中力も無くなってしまうと思います。
その合間に入る演芸は頭をリセットする上でも必要ですよね。
食事でも箸休めとかありますし。
主役より目立つことはないけれど、印象に残る芸を披露する。お客さんのテンションを維持しつつ次の噺家さんに繋げるという役割は重要ですし、やりがいがあると思います。
最後に、アコーディオンを使った演芸をやってみたい、と思ったらどうすればいいでしょうか。
アコーディオン未経験者を想定してのご回答をお願いします。
KEIKO:
音曲芸人、アコーディオン芸人と呼ばれる人口はとても少ないので、いつでも大歓迎です。
いろいろな演芸をみていただいて、好きな芸人さんをたくさん見つけて欲しいです。
好きな芸人さんがどんな先生についてどんなお稽古をしてきたか調べてまねるのも良いかもしれません。
現在はネットにたくさん情報が出ていますから。
アコーディオンの基礎はやはり、自己流よりどなたかに師事した方が絶対にいいと思います。
体の使い方や舞台の使い方など、ひとりでは行き詰まってしまいます。
舞台にバンバン出ている方でも、意外と、手に届くようなところで教えていらっしゃる方もいますので…ご自身の好きな方に師事できると良いなぁと思います。


演芸場「お江戸日本橋亭」リニューアル工事による閉館の前に、東京演芸協会の方々と撮った1枚。
左から、漫談の牧のぼる先生、コミックソングのベートーベン鈴木会長(元バラクーダ、日本全国酒飲み音頭作曲)、私、バイオリン漫談のマグナム小林先生(笑点演芸コーナーに出演)。
音ものの大先輩方に日々育てていただいています。
はらよし:
ピアノ経験者であれば自己流でもアコーディオンは弾けそう、と感じる方もいらっしゃると思いますが、アコーディオンの難しさは蛇腹にある、と言われるくらいなので、やはり一度は習って欲しいところですね。
そしておっしゃる通り、身体の使い方も大切です。
有名な方でも意外と師事できる、ということですので、チャレンジするなら思い切って憧れの師匠に声をかけるのもありですね!
KEIKO:
ぜひ、お声をかけてみてください‼︎びっくりされるかもしれませんが、嫌がる方はあまりいないのではないか…と思います。
はらよし:
そうですね。
熱意を伝えられて嫌な思いをする人はあまりいないでしょうから。
さて、名残惜しいですが、この辺りでインタビューを終わりにしたいと思います。
アコーディオンという楽器が持つポテンシャルを再確認できることも多々ございました。
貴重なお話をありがとうございました。
★KEIKOさん出演情報
「ぎふ大道芸まるけ」
10月5日、6日
オアシスパーク(岐阜県各務原市)
NHKラジオ「ラジオ深夜便~若者ききもの~」
ラジオ深夜便
10月放送予定
女流寄席(東京演芸協会主催)
10月15日
新宿永谷ミニホールFu-
クリスマスチャリティーコンサート
12月22日
江東区文化センター
◆インタビューを終えて
楽器の活用方法というのは実に多彩である、ということに改めて気づかせていただきました。
録音技術がなかった時代、音楽は聴くと同時に視ることでもあり、総合的な体験であったのだと思います。
演芸における音やリズムは、鑑賞音楽とは別の体験系、とも言えるのではないでしょうか。
演者が楽器を駆使して表現する芸は、やはりメディアを通して視聴するよりも劇場で体験して欲しい、と思います。
アコーディオンの蛇腹の動きはユニークですし、簡単にコードを弾けるベースボタンはリズムだけに使用することも可能です。
音楽家だけではなく広い意味で表現者にとっても、アコーディオンは魅力的な楽器なのではないでしょうか。
TOMBO祭をきっかけに、アコーディオンに興味を持つ人が増えてくれれば何よりです。