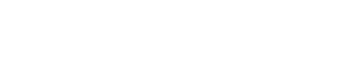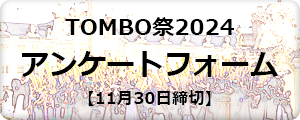株式会社トンボ楽器製作所
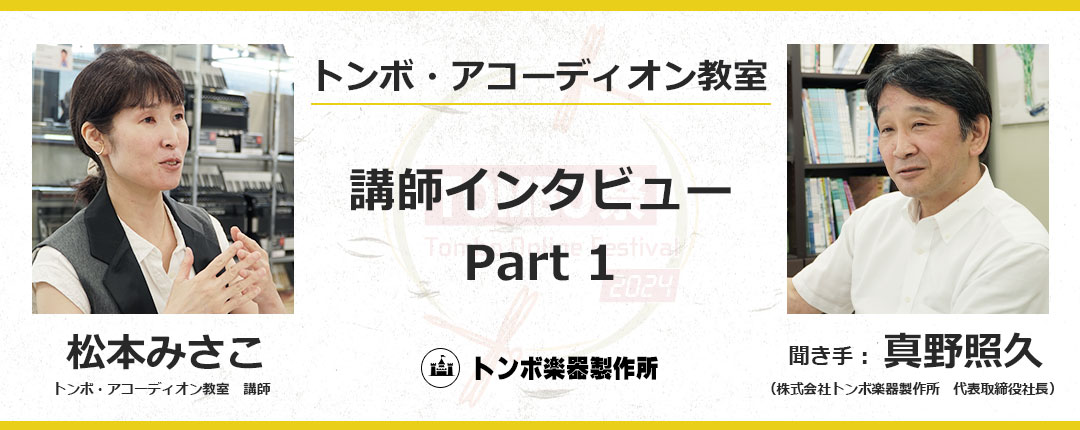
★このページは『TOMBO祭2024』のコンテンツであり、2024年11月24日時点の情報となります。
真野:
昨年はTOMBO祭第1回目ということで、弊社会長の真野泰治とアコーディオンについて色々と語り、日本におけるアコーディオンの普及に関しても触れることができたと思います。今年はトンボ・アコーディオン教室の講師お二人に、インタビューという形でアコーディオンの魅力を色々と掘り下げていきたいと思います。
まず1人目はトンボ・アコーディオン教室の講師歴18年目となる松本みさこ先生です。
松本先生、よろしくお願いします。

松本:
もう18年なんですね。
教室ではプロフェッショナルの社員と共にアコーディオンの後進の育成に務めてきました。
いい生徒に恵まれ、18年続けることができたと思います。
真野:
まず、松本先生にとってアコーディオンの魅力とはズバリ、何でしょうか。
松本:
そうですね……アコーディオンはクラシックから民族音楽まで、一台で多様なジャンルに応えられる楽器だと思います。
個人的には左手のボタンで伴奏ができることがシンプルにいいな、と思いますし、そして蛇腹の操作で多彩な表現が可能なところが魅力的だと思います。

真野:
蛇腹操作、つまりベローイング、ということですね。
私もベローイングによる表現力がアコーディオンの一番の魅力ではないかと思っています。
もちろん左手で伴奏、右手でメロディが弾けるというのもいいですよね。
あとはどんなことがありますか?
松本:
機種にもよりますが、音色の選択肢が多いところでしょうか。
たくさんのハーモニカが入っているようなものですからね。
チャンバーの音もまた魅力的です。
真野:
そうですね、スイッチで簡単に切替えも可能ですしね。
機種によって3M(MMM)だったりピッコロ(H)が入っていたりと、色々な音楽に対応できるのもいいですね。
では次の質問です。
先生がアコーディオンを始めたきっかけと、プロになる決心をした時の心情をお聞かせください。
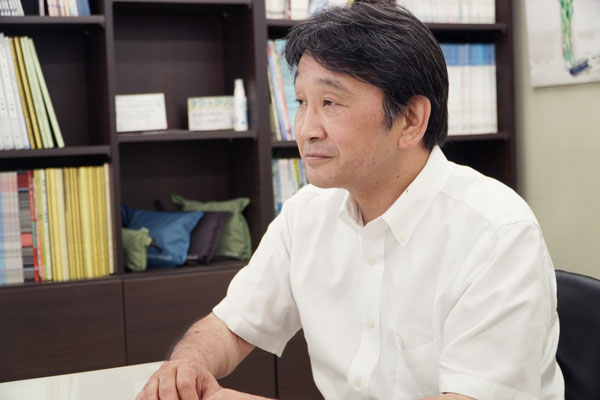
松本:
小さいころから音楽は好きでしたし、音楽に関係した仕事をしたいとは思っていました。
アコーディオンとの出会いは本当に偶然です。
音大ピアノ科の3人でオリジナルバンドを組みたくて、それぞれピアノ以外の楽器をすることに、私はアコーディオンを選びました。
新しい楽器の挑戦ということで当時はわくわくしました。
真野:
その時参考にしたプレイヤーはいましたか?
松本:
夏木マリさんとピチカート・ファイヴさんが共演している音源がありまして、「私の青空」という曲でcobaさんがアコーディオンを弾いているんですが、とても魅力的だったので、弾いてみよう、じゃなくて弾きたい! っという気持ちになっちゃいましたね。
真野:
先生は元々大学でピアノを専攻されていましたが、アコーディオンはこの時から習いはじめたんですか?
松本:
いえ、習うのは2年くらい後で、ミュゼットの巨匠たちが弾く3枚組のオムニバスアルバム(パリミュゼット)を聴いたのがきっかけです。
これは習わないとだめだな、と。
このアルバム、1日中、3年くらいずっと聴いていました(笑)
どう弾いたらこのように伝わるのかを考えていました。
真野:
(笑)
私もこの演奏には衝撃を受けました。キレが違いますね。
ミュゼットってこういう風に弾くんだ、と。
ほぼほぼボタン式ですがピアノ式であのキレを出せないかと思考錯誤しましたね……。
で、プロになろうと決心したのはいつ頃ですか?
松本:
20代後半だったと思います。
何事も1つ1つの仕事に全力投球です。
当時は1曲弾くだけで汗をかいていましたし、難しくて失敗したり恥をかいたりと、たくさんの経験をしました。
どうしたらもっと心が強くなれるのか、冷静になるにはどうしたらいいのか、など苦しんだり、アレンジに関しても難しいピアノ譜を渡されて困ったりもしていました。
でも、それでもアコーディオンが好きだったので、自分なりの理論も確立して乗り越えることができました。
そうして、いろいろなことも解決できるようになり、プロになろうと決心できました。
研ぎ澄まされた心を持ちたくて実際3ヶ月間、お寺で精神修行を体験しに行きました。
真野:
え? お寺で修行ですか(笑)
松本:
はい。邪心があったらプロになるなんて絶対無理だと思ったので。
真野:
心を清めるために山籠もりですか(笑)
松本:
そうです。
真野:
それってお寺に3ヶ月間籠ってアコーディオンを弾いていた、とかですか?
松本:
いえ、アコーディオンの練習とかではなく普通に精神修行です。
当時私はお昼に金融機関で派遣で働きながら、夜は銀座の「和尚&パトラ」(現在、四ツ谷三丁目に移転)というお店でアコーディオンを弾いていたんです。ベテランミュージシャンが日替わりでライブをしに来ていました。
ちなみに和尚さんはテナーサックス奏者でパトラさんはシャンソン歌手というお店です。
そこでシャンソンをたくさん教えていただきましたが、20代のうちにもう少しいろいろな活動をしたかったので、次の行動に移りたいと思いました。

真野:
なるほど。それでその和尚さんのお寺に行ったと。
松本:
いえ、違います。
「和尚&パトラ」の和尚さんは見た目が和尚さんみたいなだけです(笑)
真野:
そうなんですね(笑)
お一人だったんですか?
松本:
いえ、他にも安産祈願の方や離婚されて辛い方とか、人生の節目に直面した方とか初対面だけど30名くらいの方々と一緒に修行しました。
研ぎ澄まされた時間を経験できてとても良かったです。
真野:
やはりそのくらい強い気持ちがないとプロになれない、ということでしょうかね。
松本:
私としてはこの頃が一番、執着心を持っていた時期です。
真野:
なるほど。
さて、そんな修行を経験された先生ですが、独奏の他民族音楽、クラシックなどいろいろななジャンルの演奏をされていますが、今一番熱を入れているジャンルは何でしょうか。

松本:
個人的にはIsoration Orchestraというバンドで昨年アルバムを出しましたので、クレズマーというジャンルがありますが、それとお仕事で演奏する音楽は別に考えています。
私は色々なジャンルの曲をアコーディオンでどのようにアレンジできるのか、を考えるのが好きなので、そこで関わった音楽がその時点で一番熱中していると言ってもいいと思います。
真野:
ジャンルは関係ない、とにかくアコーディオンが好きで、アコーディオンを色々な音楽に入れたい、という感じですか?
松本:
そうですね。
真野:
それってアコーディオニストのある意味節操のないところですね。(笑)
何でもアコーディオンでやってしまおうっていう。
松本:
何でもチャレンジしてみたいと思っています。(笑)
真野:
クレズマーの魅力とは何でしょうか。
松本:
癒しの音楽。祈りのメロディと音階です。
クレズマーとはヘブライ語で楽士、ミュージシャンという意味なんです。主に結婚式などの慶びのセレモニーから始まりました。バイオリン、クラリネット、チンバロム、アコーディオン、コントラバス、チューバ、太鼓などなど、長年に渡る器楽の伝統です。
私は2013年、ドイツのワイマールで、80年代クレズマーリバイバルの立役者であるAlan Bern氏(ピアノ、アコーディオン)、KLEZMATICS のFrank London(トランペット)など現代においてクレズマーミュージックを牽引するミュージシャンに出会うことができました。日本でクレズマー研究をされている学者のお二人を頼りにドイツに行くことができました。大きな出会いだったと思います。
私は心が疲れた時、静かなクレズマーを弾きます。また、教室の生徒さんと気持ちを共有したい時、元気を出したい時、みんなで弾いています。
真野:
クレズマーの音楽的な特徴とは何でしょうか?
松本:
常に“オン“です。ジャズのような遅れるシンコペーションではなく、1拍目にしっかりベースがくるんです。
真野:
それはダンス的な意味でしょうか。
松本:
踏み込んだり、ターンしたりします。
真野:
音階(スケール)はどんな感じなんです?
松本:
フレイギッシュ(Freygish)スケールとかミシュゲラハ(Mi shebeirach)など、早めに増2度が来るんですが、これは早めにプレゼントを贈るという意味があったりするんです。
ちょっと弾いてみますね。
真野:
ジブシー(ロマ)音楽や中近東の音階っぽいですね。
松本:
そうですね。
トルコにも名前は違いますが同じ音階があります。
真野:
ありがとうございました。
とりあえずクレズマーのお話はこの辺で終わりにし、次の質問に移りたいと思います。
先生は色々な音楽をアコーディオンで弾いていらっしゃいますが、それらの音楽とアコーディオンの相性についてはどう感じていますか?
松本:
そうですね……相性というかそれぞれの楽器との音量の違いには特に気を使いますね。
特に小さな音の楽器と一緒に演奏するときなど。
逆にブラス系の楽器の場合はアコーディオンの音が負けてしまいますから、隙間に入れ込んだり、マイクの調整などが必要ですね。
音量のバランス調整は難しいですが、音質的な相性が合わない、というのはないと思います。
真野:
そうですね、私もハーモニカと共演するときなどは音量に気を使います。
あとはメロディスイッチを切り替えで他の楽器と被らないようにとか。
松本:
同じ音域で同じメロディを弾いてしまうのは避けたいですね。
真野:
交互に弾いたりとか役割分担は大事ですね。
アコーディオンが常に前面に出ている必要もないですからね。
ここぞ、というときに目立てればいい曲も多いと思いますし、伴奏でも入っているのとないのとではやはり入っている方がいい、くらいでも存在感はあります。
あと、全体の響きの中でアコーディオンの聴こえ方があるときは木管楽器のように、あるときは金管楽器のように変わるのも面白いな、と感じてます。

松本:
確かに、そうですね。
真野:
さて、次に参りましょう。
普段先生は教える立場ですが、逆に生徒さんから教わること、気づかせてもらうことなどはありますか?
松本:
そうですね、その前に言わせていただきたいのですが、私は真野泰治会長にアコーディオンの楽しさを教えていただいたと思っています。会長に出会えていなかったら、飽きて止めてしまっていたかもしれない、と思うくらいに影響を受けています。
メロディのうたい方やベローイングなどはもちろん、「先生、いつまでもピアノ上がりみたいな弾き方していちゃだめだよ」とか「もっと色っぽくね」とか、とてもフランクに伝えてくださったのが有難かったです。
そんな会長からの教えに私自身の経験をプラスして生徒さんには教えていますが、少しでも会長の教えのエッセンスが伝えられていればよいなと思っています。
生徒さんに気づかされたことは、それはいつもですけれど、例えば1つのことを教わると10くらいやってくる人もいて、こういう発展的な姿を見ると私もまだまだ成長できるはず、と感化されています。

真野:
生徒さんにもいろいろな方がいらっしゃいますから、やはり大変なことも多々あるかと思います。
松本:
そうですね……私が知らないアーティストの曲を譜面にして欲しい、という要望もあって、逆にこんないい曲があったんだと教えてもらうこともあります。
特にビギナーの方に話したいことは私のアコーディオンの基本理念は蛇腹を太く使うことで、本質を知っていけば、蛇腹を無理に引っ張った音を出す必要もないと思います。
あと、細かいフレーズがはっきり聞こえない生徒に対して、もっとゆっくり、はっきり、隣の音がもつれちゃわないように、浅く軽く弾いてください。と常に言っています。それが理解できれば音も変わるし、上達すると思います。
私は極端な話、“先生“としては好かれなくていいのですが、”信頼“されなければ上達もないと思っています。
楽器演奏を挫折しないためのモチベーション維持など、いろいろあると思うんですがそれはまたの機会にお話させていただきたいと思います。
真野:
ありがとうございます。
では次に参りましょう。
アコーディオンの上達には何が一番大切だと思いますか?
先生の経験則でよいのでお聞かせください。
松本:
(笑)これは人それぞれ違いますからね。
音楽をよく聴くこと、でしょうか。
歌やリズムを感じ、それを表現することが大切なのかなと思います。
真野:
そうですね、それは曲を仕上げていく段階では必要になってくることだと思いますが、もっと初期の段階ではどうでしょうかね。
練習しかない、と言われればそうなんですが(笑)
その練習をどうしたらより効果的にできるかという意味で。
松本:
社長はどうお考えなんですか?
真野:
やはり大前提にアコーディオンが好きだ、ということ、そしてどうしても弾きたい曲があって、それを弾くためにはこんな練習が必要だ、という風に考えることが継続できるかどうかの分かれ目なんじゃないでしょうか。
練習が苦に感じないくらいにアコーディオンや曲が好きになれるか、ですかね。
あと、演奏にはそれを弾くために必要な筋肉があって、練習をしていないと衰えてきてしまうと思うんです。弾けることは弾けても弾き続けることが、疲れてしまって出来なくなりますね。
松本:
持久力、確かに必要ですね。
真野:
それはやはり反復練習しかないのでは、と思います。
松本:
必要だと思えるかどうかが重要ということですね。
真野:
そうだと思います。
松本:
昔、ベローシェイクを16小節やらなければならない、という曲があったんですが、当時は出来なかったんです。
それが4年後、普通にできるようになっていたんです。
余分な力が抜けて尚且つ、蛇腹が広がらないようにすることができたんです。
これはそれを可能にするための左側の筋肉がついたということだと思いますし、実際左側の腕が大きいんですよ(笑)
真野:
いろいろな曲を経験することによってできなかったことが、いつの間にかできるようになっている、ということはありますね。
無駄な力が抜ける、というのは大きいと思います。
一日にまとめて練習、というより毎日コツコツするのが大事かもしれません。
あと、基礎練習だけで終わらずに、必ず曲をやることでしょうか。
松本:
そうですね。
あとコントロールや表現力がつくので立奏の演奏も大切だと思っています。
真野:
ありがとうございます。
では次の質問です。
アコーディオンは重たい楽器ということで、興味はあるのに躊躇される方もいますが、かなり高齢の方でも楽しんでいらっしゃいます。
この重さとどうつきあうのか、重さを気にして迷っている方へメッセージをお願いします。

松本:
これは慣れるしかないですかね。(笑)
あと、演奏している時はあまり気にならないと思います。
真野:
そうですね、運ぶときと持ち上げる時だけですよ、重さを感じるのは。
弾いている時は全く感じませんよね。
少なくとも座って弾けば問題ないでしょう。
松本:
そうだと思います。
真野:
ありがとうございます。
では次で最後の質問となります。
これまで出演したライブやコンサートで、特に印象に残っているステージとその理由を教えてください。
松本:
私は夢半ばで、どれも反省が残るのですが、今年(2024年)の3月にプリム祭でクレズマーを演奏したことでしょうか、Purim祭といって春に行われる、昔々紀元前の戦いの勝利を祝うお祭りなんです。
久しぶりにジンタラムータのメンバーとして、演奏させていただきました。
独特のリズムHoraの伴奏がうまくなったと褒めていただきました。10年目にしてやっと板についてきた気がして、まだこれからですがホッとして少し自信がつきました。
真野:
場所はどこだったんですか?
松本:
東京・広尾のシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)です。
真野:
やはり継続は大事ですね。
それには好きという気持ちと共に情熱も継続できないと結果が出てこない、ということなのかと思います。
それでは、この辺りでインタビューを終わりにしたいと思います。
本日は楽しく、そしてためになるお話をありがとうございました。
今後もトンボ・アコーディオン教室をよろしくお願いします。
松本:
こちらこそ、有意義なお時間をありがとうございました。