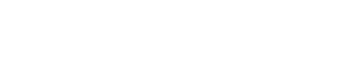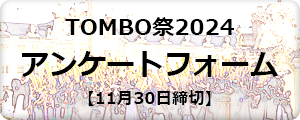株式会社トンボ楽器製作所
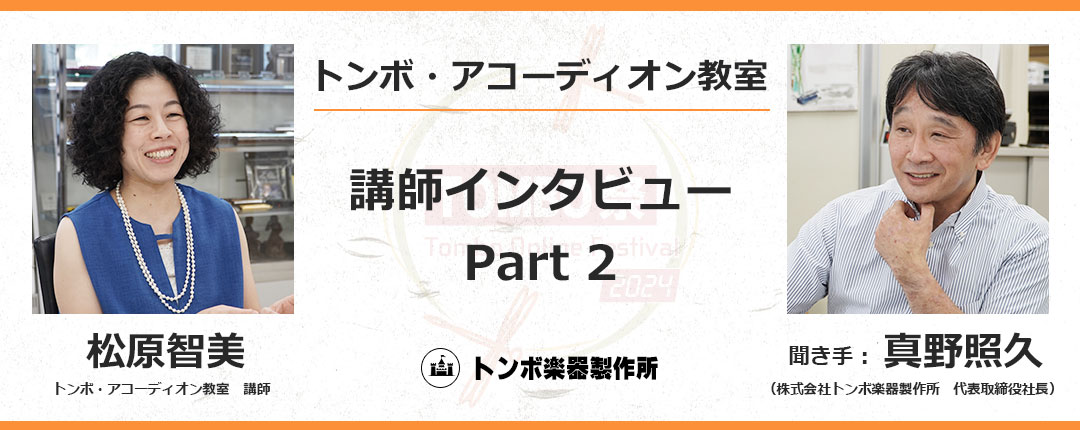
★このページは『TOMBO祭2024』のコンテンツであり、2024年11月24日時点の情報となります。
真野:
昨年はTOMBO祭第1回目ということで、弊社会長の真野泰治とアコーディオンについて色々と語り、日本におけるアコーディオンの普及に関しても触れることができたと思います。
今年はトンボ・アコーディオン教室の講師お二人に、インタビューという形でアコーディオンの魅力を色々と掘り下げていきたいと思います
トンボ・アコーディオン教室は令和3年より講師2人体制となりました。
ということで、新講師の松原智美先生にインタビューをさせていただきたいと思います。
松原先生、よろしくお願いします。

松原:
よろしくお願いします。
真野:
まずはじめの質問は松本先生と同じです。
松原先生にとってアコーディオンの魅力とはズバリ、何でしょうか。
松原:
そうですね……アコーディオンは音を出した後に変化させられる、というのがとても大きな魅力かと思います。
そして電源が必要なく、持ち運べるサイズなのにあれだけの音量が出せて、ソロも伴奏もできる、というのは素晴らしいと思います。

真野:
音を出した後にベローイングで変化をつけられるのは本当にそう思います。
でもそれが難しいところでしょうけれど。
松原:
そうですね。難しいですね。一番難しいところであり、面白いところだと思います。
真野:
では次の質問です。
松原先生はボタン式アコーディオンをメインで使用されていますが、ボタン式の特徴など教えていただけますでしょうか。
ピアノ式と比較しても結構です。
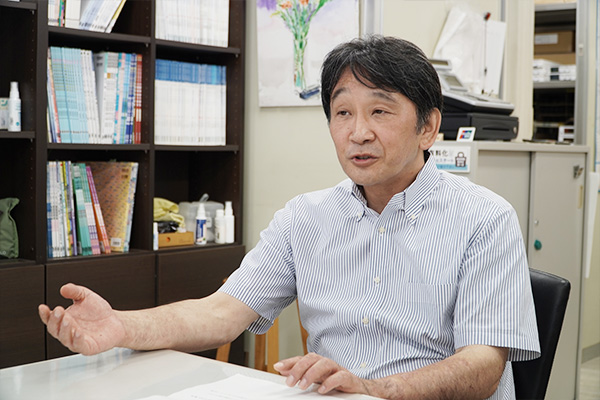
松原:
私は18歳の時にフランスへ留学したんですが、そのときは鍵盤式(ピアノ式)を持っていきました。渡仏後にフリーベースを習いたい、と先生に相談したら右手もボタンにすれば、と言われたんです。
フランスは皆ボタン式ですからなぜ右手だけ配列の異なる鍵盤式をやるのか、という感覚なんです。
それがボタン式に移行したきっかけです。
結果的に良かったのは私は手が小さいので間隔の狭いボタンの方が押さえやすいところと、広い音域がとれることですかね。
ただ難しいところもあって、指使いの選択肢がピアノ式に比べると多いので、どれが最適か考えなければいけないんです。
指使いを書かずに弾けるようになるまで4年くらいかかりました。
真野:
それはやっぱり5列のボタンをフルに使う、ということですか?
松原:
私の場合はそうですね。
目的によっては重複している4、5列目を使わずに手前の3列でもいいんですが、
弾きやすさを考えると5列使うことになりますね。音ミスの少ない指使いにすることを考えるとそうなります。
真野:
3列だと転調したときの指使いは同じなので便利ですよね。
松原:
そうですね。
ただ、白鍵のグリッサンドはピアノ式ならではですよね。
ボタンでやるとディミニッシュになってしまうんで(笑)
真野:
そうですね(笑)
松原:
やはり曲を作った人のシステムは影響しますね。
フランスのミュゼットとかはボタン式が弾きやすいと思いますし。
真野:
そうですね。
では次の質問に行きましょう。
松原先生はドイツの国立芸術大学でアコーディオン専門の教育を受けていますが、そこでしか得られない、と感じた経験などをお聞かせください。
松原:
日本には専門のアコーディオン学科がありませんが、ドイツにはいくつかアコーディオン学科があり、そこでは音大と同じようにアコーディオンのテクニック以外に音楽全般について学ぶことができます。
日本だと同世代でアコーディオンを学ぶ人とはほとんど出会えませんが、そこには色々な国の人が来ていますので、たくさん刺激をもらえます。
ドイツはクラシックはもちろん現代音楽も盛んな国なので、最先端のテクニックを学ぶことができますし、他の楽器とアンサンブルをする機会にも恵まれています。

真野:
やっぱりドイツがいいですか?
松原:
他の大学に行ったわけではないので分かりませんが、教育機関としてはしっかりしていると思います。
フランスにアコーディオン専門の学科ができたのは結構遅くて、私が渡仏してから4~5年くらいしてからでした。
真野:
御喜(美江)先生に教えていただいたのはドイツですか?
松原:
そうです。
真野:
日本語で?
松原:
いえ、ドイツ語ですけどたまに両方混ざります(笑)
真野:
先ほど大学にはいろいろな国の人が来てる、とおっしゃいましたが、具体的にはどこですか?
松原:
ドイツ人は1人もいませんでしたね(笑)
私が行ったときはセルビア人が一番多かったです。
東欧ですね。ブルガリアとかロシアとか。
あとはフィンランドやオーストリアとかも。
今は中国も多いみたいです。
真野:
中国の方、上手いですよね。
配列はBが多いんですか?左右対称の。
松原:
そうですね、大学ではどの配列を弾いているかは関係ありませんが、B配列が多かったです。
御喜先生はピアノ式ですし。
真野:
日本はC配列が多いですよね。
松原:
そうですね。あと、フィンランド配列もありましたよ(笑)
真野:
ところで、どうしてこんなに多くの種類の配列があるんでしょうか。
その国の曲が弾きやすいとかですかね。

松原:
それはよく分かりませんが、どの国も独自に改良してたみたいです。
真野:
規格統一の話はなかったんですか?
松原:
そういう動きはあったみたいですが、どこも自分の国の配列が一番、ということで実現はしなかったようです(笑)
真野:
それはそれは……(笑)
では次の質問にまいります。
松原先生がアコーディオンを弾き続けるモチベーションはどこにありますか。
松原:
モチベーションですか、そうですね、私は演奏者と講師、両方していますがどちらも必要だと思っています。
演奏者だけで生活するのは経済的に厳しい、という現実もありますが、両方のバランスが大事かなと思います。
やはり表現したいという気持ちがあるので自分の演奏活動のために練習をするわけですが、そこで気づいたこと、姿勢やテクニックについてはレッスンにも活かせますし、どちらの活動も相互に影響しあって弾き続けるモチベーションに繋がっている気がします。
真野:
なるほど。ところでドイツの学校では“教え方”についても学ぶのでしょうか。
松原:
いえ、私は演奏科だったので教わっていません。
教育系の学科もありましたが私は勉強していませんので、教え方については帰国後にこれまでの経験などを踏まえて考えています。
真野:
松原先生の生徒さんはみな姿勢がいいですよね。
あと音の出し方がしっかりしている感じです。
やはり基礎的な部分を重視されているのかなと。
松原:
そうですね。基礎は大事ですからね。
ちゃんと楽器を支えられていない状態で何かしようと思っても、それは難しいですよね。
楽器を安定して持てるかどうかが鍵です。
大人の生徒が多いので、頭で理解してから身体を動かしてもらうことも多いです。
とにかく自分で工夫できるようになってもらいたいという思いがあるので、工夫できる箇所やポイントになる着眼点を伝えて、鏡を使って自分の姿を見たり、録音して音を聴いたりして自分自身を観察することは重視しています。
真野:
逆に生徒さんがアコーディオンを続けるモチベーションってどこにあると思いますか?
モチベーションというか動機ですかね。
人によって色々あると思いますが。
松原:
私はレッスン初日に、どうして習おうと思ったのか、動機を必ず聞くんですが本当に皆バラバラです(笑)
例えばディズニーリゾートでの演奏を聴いて、とか最近だとYouTube動画を観て、とか。ご年配の方ですと昔からの憧れだった、というのも多いです。
真野:
時代によっても人によっても様々ですね。
分かりました。では次の質問に参ります。
松原先生はこれまで多くのステージを経験されていますが、特に印象に残っている演奏についてお話しください。
松原:
そうですね、たくさんあるんですが金沢にある『鈴木大拙館』という博物館での公演は印象的でした。
ここに『水鏡の庭』と呼ばれる、水を張った幻想的なスペースがあるんですが、ここで舞踏とのコラボレーションをさせていただいたんです。
水のすぐそばで演奏するんですが、凄く響くんですよね、水を張っていると。
演奏会は夜でしたが、照明はほとんどなかったのも幻想的でした。
あと、実は譜面灯が点かなくて楽譜が見えなかったんです。(笑)

真野:
え! 大丈夫だったんですか?
松原:
ギリギリ大丈夫でした。(笑)
真野:
よかったです。でも焦りますよね。
ここ、屋外ですが音響はどんな感じだったんですか?
松原:
無いです。生音でとても響くんです。
真野:
なるほど。
水が音に与える影響については昔何処かの記事で見たことがあります。
松原:
『鈴木大拙館』は建築物としても有名ですので、あのコンクリートも影響しているかもしれませんね。
とにかくシチュエーションも非日常的でしたので印象に残っています。
真野:
ところで、松原先生は『ひとひらの水彩』というアルバム(CD)を出されています。
クラシックは基本的にマイクを使用しないと思いますが、この作品のレコーディングは当然マイクを使用していますよね。
松原:
はい。エンジニアさんもそこに拘りのある方でして、普通は右手左手で分けたりすると思いますが、ステレオマイクを1本だけ立てて音を録りました。
真野:
なるほど。よりリアルに近い感じでしょうか。
話は変わりますが、先生は何歳からアコーディオンを始められたんですか?
松原:
ピアノが5歳でアコーディオンは8歳から始めました。うちは母がアコーディオンを弾いていまして、私が寝ている頭の上で弾いてた、と言っていましたね(笑)
今いるアコーディオニストの中にも親がアコーディオンを演奏していたり、家に楽器があった人って多いですよね。
身近に楽器があるというのは、この楽器を始めるのに大きな要因になっていると思います。
真野:
cobaさんも檜山(学)さんも大田(智美)さんもそうですね……。
気が付いたらアコーディオンを弾いていた、みたいな(笑)
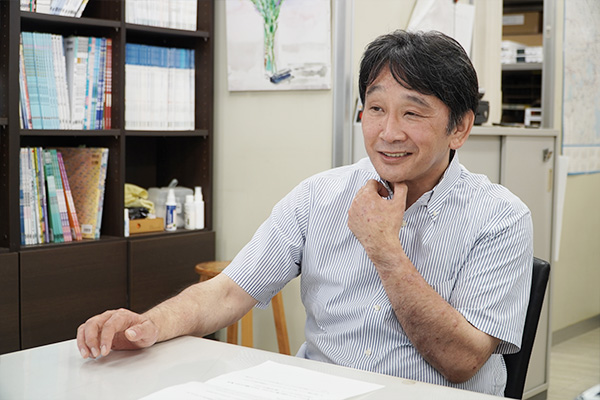
松原:
それはそうでしょうね(笑)
真野:
では次の質問に行きましょう。
先生はブログやYouTubeを通し、教室で教わるような内容も発信されていますが、その意図はどこにあるのでしょうか。
松原:
ブログの方ですが、まず私自身が自分の姿勢(フォーム)を変えよう、と思って色々と試行錯誤をしているときに色々な発見がありまして、自分の記録用に書いていたんです。
その後、コロナ禍があって対面レッスンができない時期に生徒さん向けの補助教材として書き始め、その時はYouTubeも限定公開でした。
それを整理して一般公開していった感じです。
真野:
その動画を観て習いに来た方もいますよね。
松原:
いますね。アコーディオンに関する動画も少なかったですし、楽譜もほとんどないですからね。
もちろん動画で全てを伝えることはできませんけれど。
真野:
そうですね、基本的なことを説明しているのはいくつかありますけど、それだけではやはり分からないですし、色々と疑問も出てくるでしょうから、やはり教室で習うことが必要かと思います。
松原:
独学の方もいらっしゃいますが、そえぞれの考え方なのかな、と思います。
自分で色々と開拓するのが好き、という方は独学でもいいと思いますが、早く弾けるようになりたい場合は、習った方が絶対いいですね。
ただアコーディオンの場合は全国に先生がいるわけではないので、ブログや動画がそういう人の参考になればと思っています。
なので習える人は習ってください(笑)
真野:
そうですね。(笑)
そうしてアコーディオンを習い始め、アコーディオンを購入しようという時ですが、輸入アコーディオンを新品で購入するとなると、それなりに高額になります。
購入時に押さえておきたいポイントや、心構えをお聞かせください。
松原:
試奏ができることを前提にお話ししますと、音色が自分の好みかどうか、は大事だと思います。
メーカーの違いだけでなく同じ機種でも個体差がありますからね。
あとはそのスペックが本当に必要かどうか、というのも大事です。
例えば柔らかいトーンの出るチャンバーという機構がありますが、これがあるだけで重量も増えて高額になります。
あとストラップ(背負いバンド)の幅も重要です。
大きい楽器には幅の広いものが付いていますが、女性だと合わないこともあります。
真野:
そうですね、欧米基準なのでそれはあるかもしれません。
松原:
あとは他の人を連れて行って、客観的な意見を聞くことですかね。自分では気づけないところを指摘してくれたりします。
試奏できない環境の方は……
発注することになるのでカスタマイズができるのがいいですね。
ボタンの色も変えられますから自分好みに合わせることもできます。
真野:
そうですね。
色々なケースがあるとは思いますが、初めて購入するアコーディオンに関してはどうお考えですか?
いきなり高額商品を買ってしまって、それがモチベーションに繋がる人もいると思います。
松原:
私の生徒さんの場合、始めはアコーディオンを持ってない方が多いので、まずレンタルからです。
1年レンタルして色々分かってから購入してもらうのがいいと思っています。
ただ、レンタルだと気を使うから早く買いたいという方もいらっしゃいます。
そういう場合は、予算と大きさを聞いて私が選ぶことにしています。
今はネットのフリマサイトを利用して買う方もいるんですが、やはりお薦めはできないですね。
真野:
笛の数はどうです?
スタンダードなMMLでいいのか、それともピッコロが入ったHMMLにすべきかなど悩ましいと思います。
松原:
ピッコロは……なくても何とかなるかな(笑)

真野:
そうですね、私もピッコロはなくても大丈夫かな、と思います。
もちろん曲によっては必要なこともありますが、通常はなくてもいいかなと。
鍵盤数はどうですか?
松原:
それはその人の体力次第じゃないでしょうか(笑)
37鍵は必要と思いますが、それでも重いという方もいらっしゃいます。
真野:
37鍵は標準ですかね。
上達してくれば少ない鍵盤でもアレンジで弾ける曲が増えると思いますが、かなり上級者でないと難しいかな、と思います。
ボタン式はコンパクトですし、元々音数も多いですね。
松原:
そうですね。最大のもので5オクターブ以上出ます。
真野:
ボタン式は外見上小さいので軽そうに見えますが、重いんですよね。
松原:
そうなんです!
みんな軽いと思ってますが、中に入っているリードも増えるし重いです(笑)
真野:
ということで、話が脱線しましたが、購入する際はできるだけ試奏する。
そしてネットに出品されているものには気を付ける、ということでしょうか。
松原:
そうですね。特にネットで出所が不明な品はジャンクと表示されていなくても酷いものがありますので。
真野:
もしどうしてもその機種が欲しい場合は、買っても修理代が凄くかかってしまうか、修理自体ができない可能性があることを理解して、ということですね。
それでは次に参りましょう。
今後の活動について、そしてアコーディオニストとしての目標をお聞かせください。

松原:
目標……ですか。
そうですね、奏者としては常に何かしら課題がありますので、それにコツコツ向き合っていくしかないかなと(笑)
ゴールはあってないようなものですから。
教えることに関しては、マニュアルを作れればいいなと思っています。
初心者が来た際に、何となくやることは分かっているんですがもう少し整理しておきたいな、と。
真野:
生徒さんによっても変わりますから大変そうですね。
松原:
そうですね、なので“傾向“くらいしかまとめられないですけどね。
真野:
私が習っていたときは基礎練習を1時間とかありましたけど、どう思います?
松原:
私が新米講師だったときですが、私と生徒さんとで考え方のミスマッチがありまして、結果やる気をなくされちゃったことがありました。
フリーベースをやりたいということだったので、凄くやる気のある人だと思って熱をいれて教えてたらそうでもなかったみたいで……。
そんなこともあって、子どもではなく大人に教える、ということを考えると練習時間も限られますから、その人の生活スタイルに合わせた課題を出すようにしています。
1週間のうち、どのぐらいの時間を練習に割けるかを聞いて宿題を出しています。
真野:
そうなんですね。
あと、楽譜を読めない生徒さんもいると思いますが、どのように教えていますか?
松原:
楽譜はやっぱり読める方がいいので、基礎練習と並行して教えています。
鍵盤経験のない大人の方だと指が中々動かないので、そういう練習も必要ですね。
真野:
逆にピアノがとても上手なのに、アコーディオンになると思うように弾けない、という方もいますね。
松原:
蛇腹操作が上手くできないと弾けないですからね。
生徒さんにも蛇腹を開けることに苦労する人もいます。
力の入れ方が違うんでしょうけど、驚くほど開けられない人がいます。
蛇腹が思うように開けられない人は力の入れる方向が内側なんです。
自分の体内に力を入れてしまって(力んで)、蛇腹には全く力が伝わっていないことはありますね。

真野:
なるほど。
蛇腹操作って意外と力がいるみたいですね。
松原:
子どもでも弾ける楽器なので、本来そんなに力はいらないはずなのですが、大人の場合は思い込み(勘違い)と使い慣れていない身体というのはあるかもしれません。
小さいころからやっていると感じないですけどね(笑)
真野:
とはいえ、普段は使わない筋肉なので、弊社でも技術者を育てる時にアコーディオンも弾けるように指導しますが、蛇腹側の脇が筋肉痛になるみたいです(笑)
松原:
そうなんですね。
だから最近は蛇腹の動かし方から教えるようにしています。
蛇腹ができなければ鳴らない楽器なので、指よりも腕と背中を使うことを先に教えています。
真野:
ところで、先生は生徒さんの中からアコーディオンの世界チャンピオンが誕生してほしい、と思っていますか?
松原:
いやー……そういうのは特にないですが、先生になる人が増えて欲しいと思っています。
アコーディオンの先生、少ないので。
真野:
そっちの方なんですね。
確かに習いたくても住んでいる場所に先生がいない、という状況は減らしたいです。
さて、ではそろそろ最後の質問にいきたいと思います。
アコーディオンに興味があるけど中々一歩を踏み出せない、という方に何かメッセージをいただけますでしょう。
松原:
やはり体験レッスンに参加したり、楽器店に行って実際に持って、触って音を出してみるというのがいいですかね。
真野:
そうですね。そういう場を私たちメーカーも作っていかなければなりませんね。
松原:
とにかく実際に触れることが大事かと思います。
もともと「音楽の知識がなくても弾ける」というコンセプトで誕生した楽器なので、音を出すのはそれほど難しい楽器ではないんです。身近に習うところがなければ、YouTubeを見てみたりオンラインレッスンをしているところを探したりしてみてください。
指に注目しがちですが、これまでも申し上げてきたように楽器を安定して持つことが上達の鍵なので、動画を見る場合もそこに注目して取り組んでみると、独学でも演奏できるようになると思います。
真野:
ありがとうございます。
アコーディオンを置いている楽器店は限られていますが、都内に来た際には観光のついでに立ち寄る、という軽い気持ちでいいので、トンボ楽器ショールームに遊びに来て欲しいですね。
それでは、この辺りでインタビューを終えたいと思います。
本日はインタビューというよりアコーディオン談義となりましたが、楽しいお時間をありがとうございました。
今後ともトンボ・アコーディオン教室をよろしくお願いします。
松原:
こちらこそ、ありがとうございました。
宜しくお願い致します。